【1987年のゲーム史】 次世代”が玄関をノックし、物語が歩き出した年
 0
0
1987年のゲーム史。ハードでは最終的に1000万台以上を販売した「PCエンジン」がこの年に発売されました。セガは、前年に海外で展開していた「セガ・マスターシステム」のマイナーチェンジ版を日本で発売。ゲームでは「ファイナルファンタジー」の第1作目が発売された年でした。
NECとハドソンが送り出したPCエンジンは、ファミコンの隣に“未来”を置き、『ファイナルファンタジー』『女神転生』『ドラゴンクエストII』は、 “物語を進める”という感覚をプレイヤーに届け始めます。
この年、ゲームは“何をするか”ではなく、“どこへ向かうか”を問い始めました。
1987年を、日付とともに振り返っていきましょう。
1月14日 家庭用『リンクの冒険』(任天堂)発売
“続編”は、前作をなぞらない。
『ゼルダの伝説』の続編として登場した『リンクの冒険』は、
見下ろし視点から横スクロールアクションへと構造を一新。
“続編とは、前作の焼き直しではない”という任天堂の姿勢が、
プレイヤーに“変化を受け入れる楽しさ”を教えてくれました。
1月26日 家庭用『ドラゴンクエストII 悪霊の神々』(エニックス)発売
“世界が続いている”という感覚。
『ドラゴンクエストII』は、前作から100年後の世界を舞台にしたRPG。
パーティ制、船による移動、複数の町とダンジョン――
“冒険の広がり”と“物語の継承”が、シリーズという概念を定着させました。
6月20日 アーケード『ドラゴンスピリット』(ナムコ)稼働開始
“竜になる”という変身願望。
『ドラゴンスピリット』は、竜に変身して戦う縦スクロールSTG。
地上と空中の撃ち分け、巨大ボス、ファンタジー世界――
“人ではない存在になる”という没入感が、プレイヤーを引き込みました。
7月10日 家庭用『夢工場ドキドキパニック』(任天堂・フジテレビ)発売
“テレビ局とゲーム”の異色コラボ。
『夢工場ドキドキパニック』は、フジテレビのイベントと連動した横スクロールアクション。
後に『スーパーマリオUSA』として海外展開されるこの作品は、
“IPとゲームの融合”という新たな可能性を示しました。
9月11日 家庭用『デジタル・デビル物語 女神転生』(ナムコ)発売
“悪魔と会話する”という異端。
小説を原作とした『女神転生』は、悪魔を仲魔にし、合体させるという独自のシステムを導入。
“敵と戦う”だけでなく“交渉する”という選択肢が、
RPGに“倫理”と“選択”という新たな軸を持ち込みました。
10月18日 家庭用『セガ・マスターシステム』(セガ)発売
“8ビットの完成形”を掲げた挑戦。
『セガ・マスターシステム』は、マークIIIの上位互換機として登場。
FM音源、連射機能、3Dグラス対応などを標準搭載し、
“性能で勝つ”というセガの姿勢を明確に打ち出しました。
10月30日 家庭用『PCエンジン』(NEC・ハドソン)発売
“次世代”が、ついに姿を現した。
『PCエンジン』は、8ビットながら16ビット級のグラフィック性能を誇る新型機。
Huカードによる小型ROM、アーケード移植の完成度、
そして“NEC×ハドソン”という異色のタッグが、 “ファミコンの次”を現実のものとして提示しました。
◽️ローンチタイトル
・上海(ハドソン)
・ビックリマンワールド(ハドソン)
12月18日 家庭用『ファイナルファンタジー』(スクウェア)発売
“最後”のつもりが、最初の伝説に。
『ファイナルファンタジー』は、当時経営危機にあったスクウェアが“最後の賭け”として送り出したRPG。
ジョブ選択、飛空艇、クリスタル、そして植松伸夫の音楽――
“物語を進める”という体験が、ここから始まりました。
結果としてこの“ファイナル”は、シリーズの“スタート”となり、
以後のRPG文化を大きく塗り替えていきます。
1987年は、“次世代”が玄関をノックし、“物語”が歩き出した年でした。
PCエンジンが“未来”を名乗り、ファイナルファンタジーが“伝説”を始め、
女神転生が“異端”を許し、ドラゴンクエストIIが“世界の継承”を示しました。
ゲームは、ただの遊びではなく、“続いていくもの”になり始めていました。
FF9 祝25周年!縄跳び1000回チャレンジ!?
コメント
まだコメントはありません。コメントを追加してみましょう!
ほのぼの情報「ぽんぷー」(外部サイト)

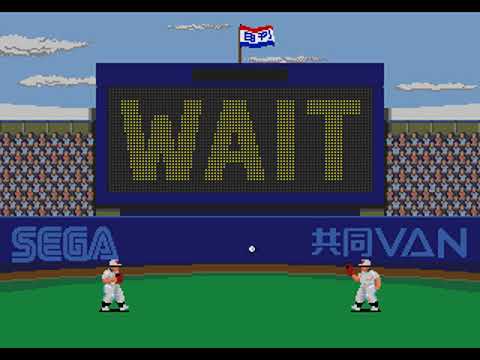






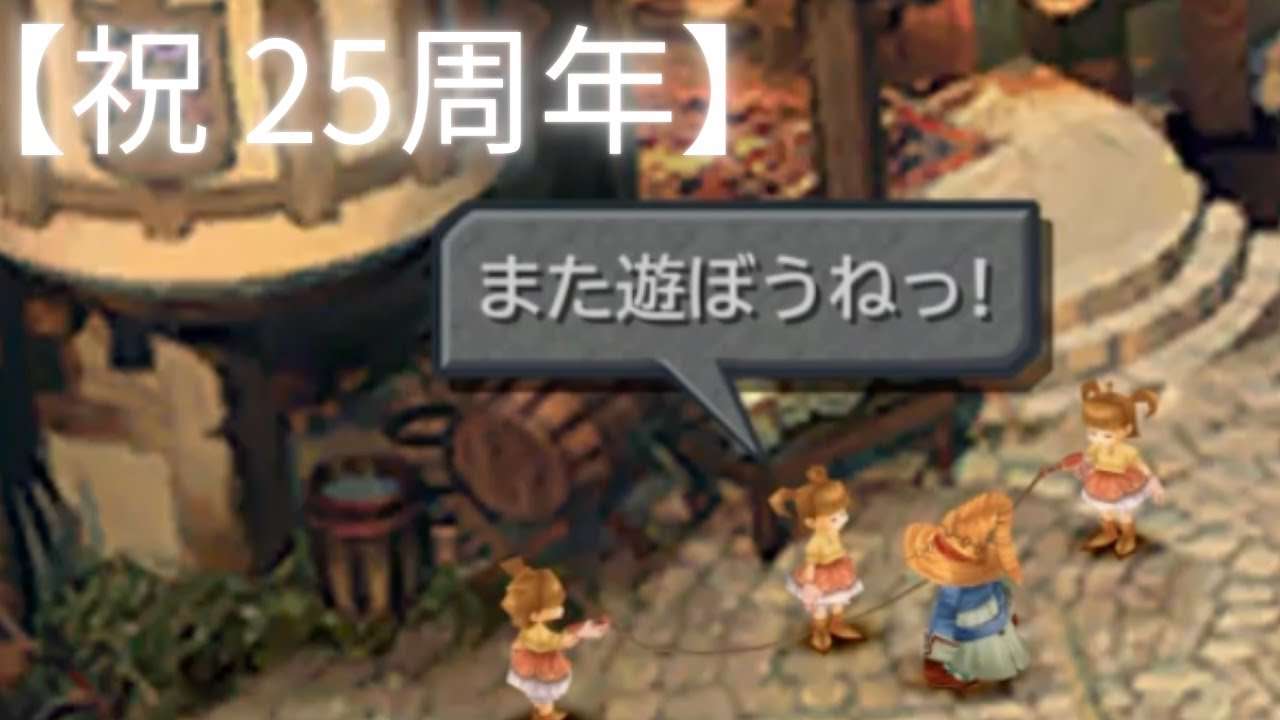
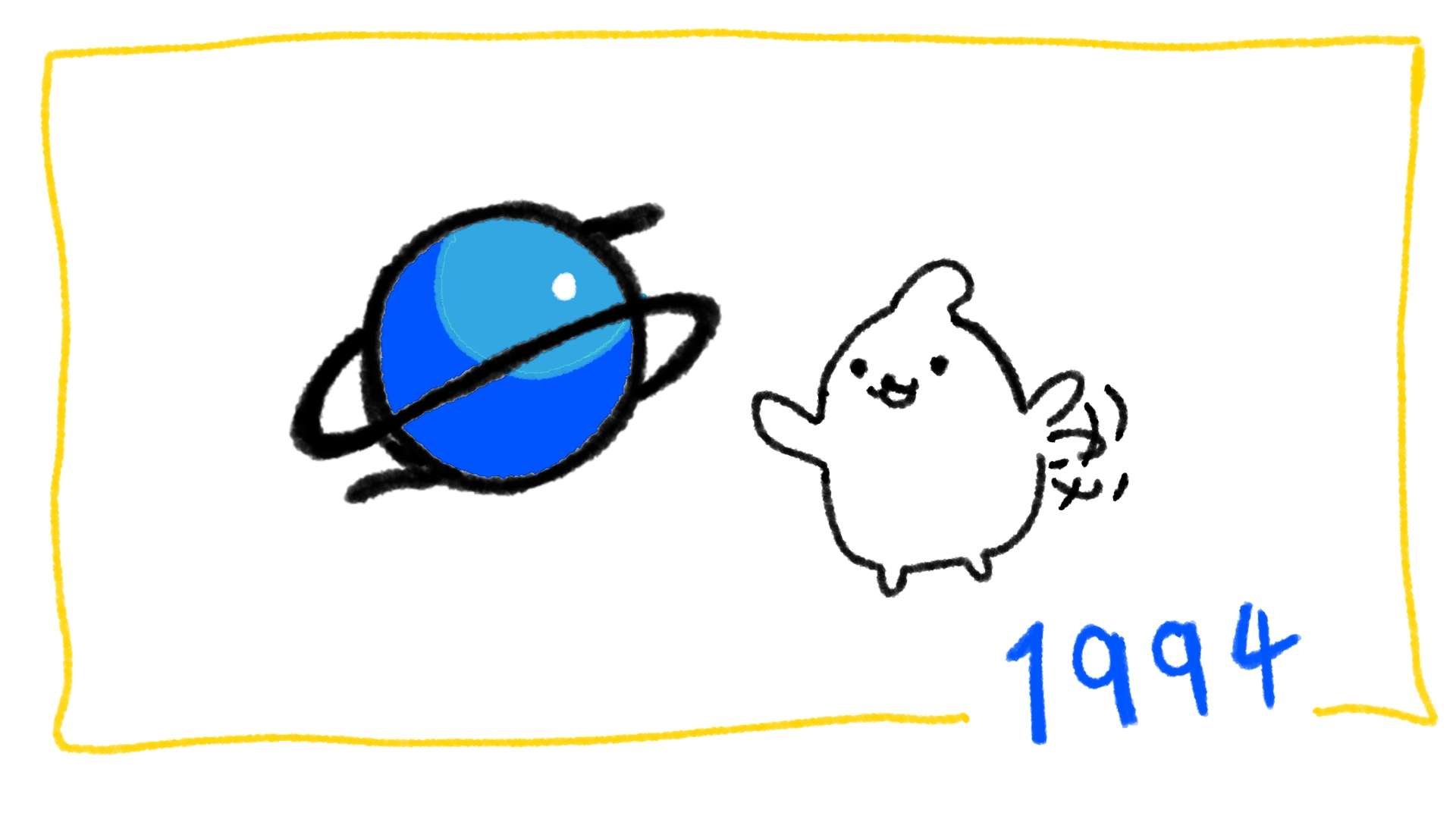
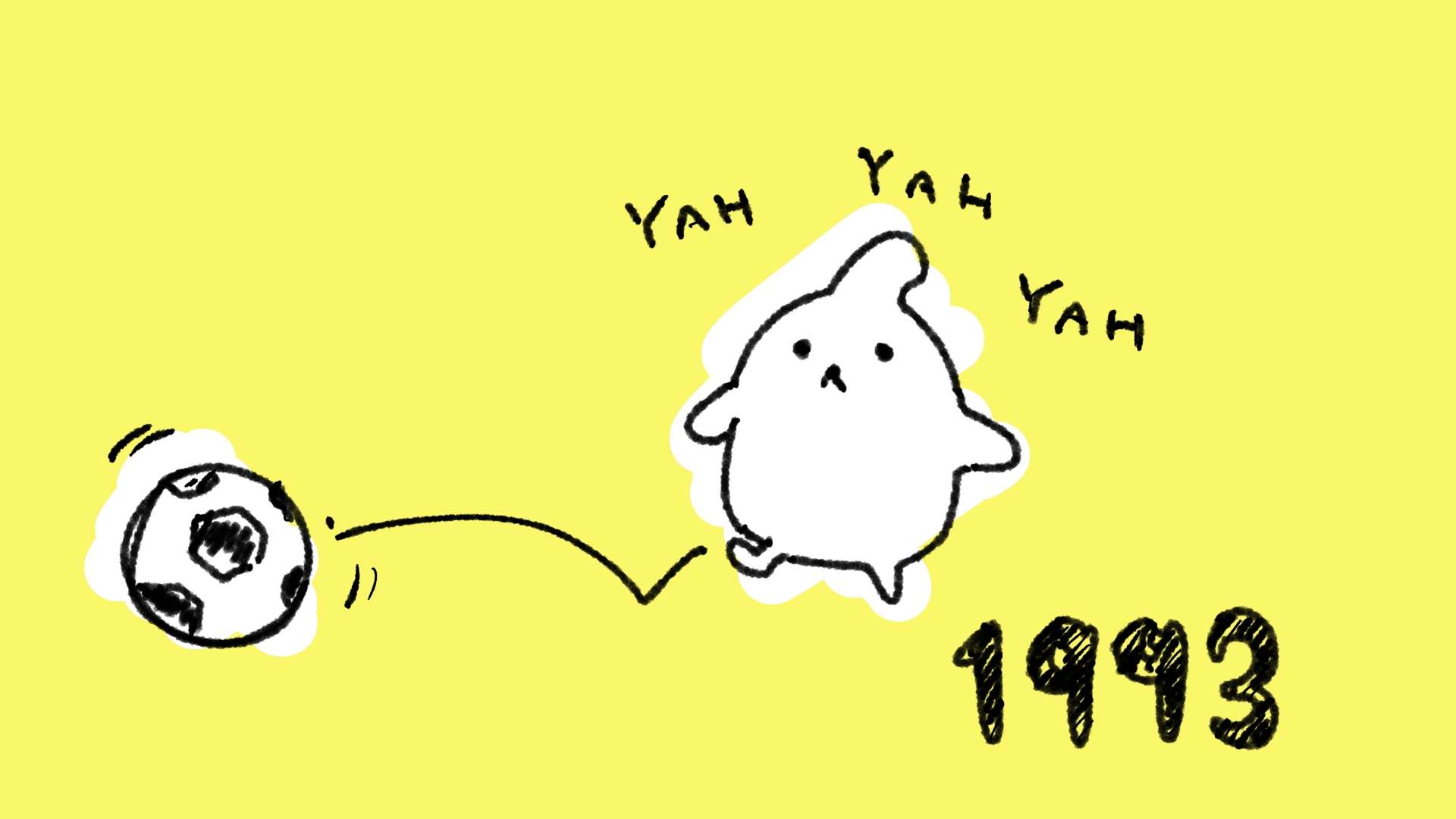
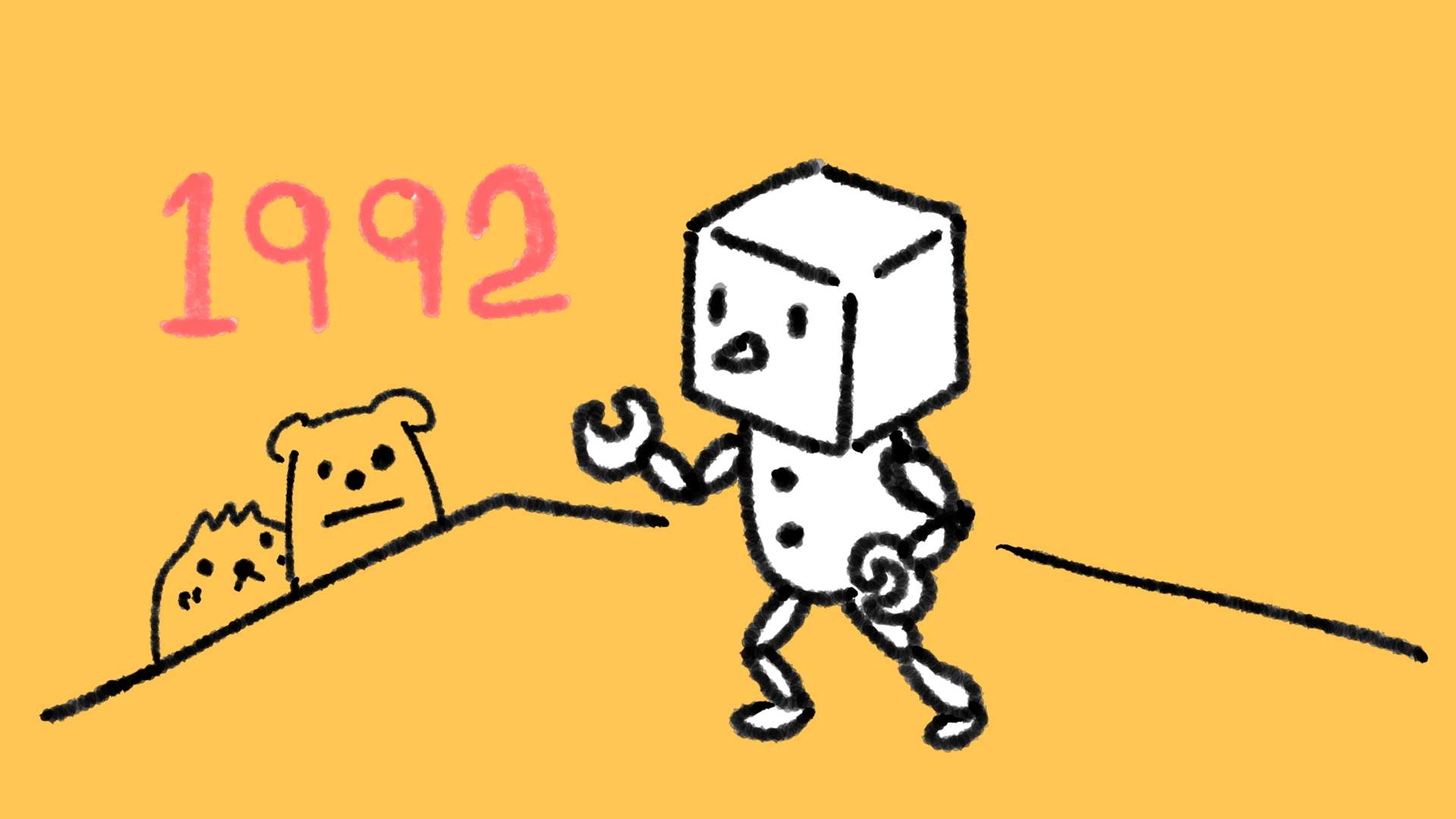



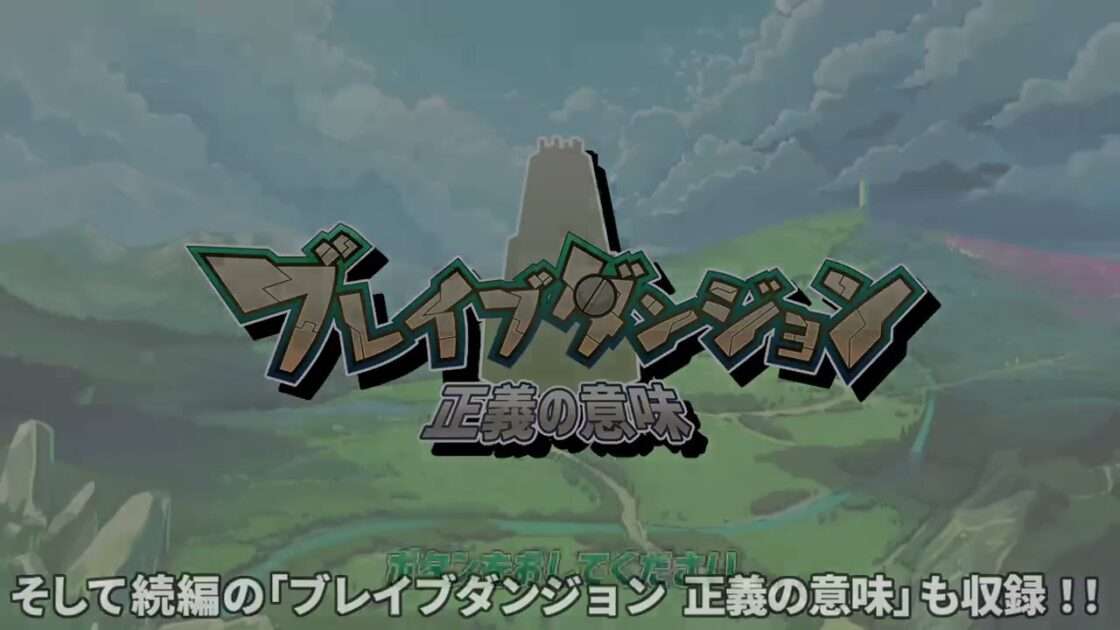

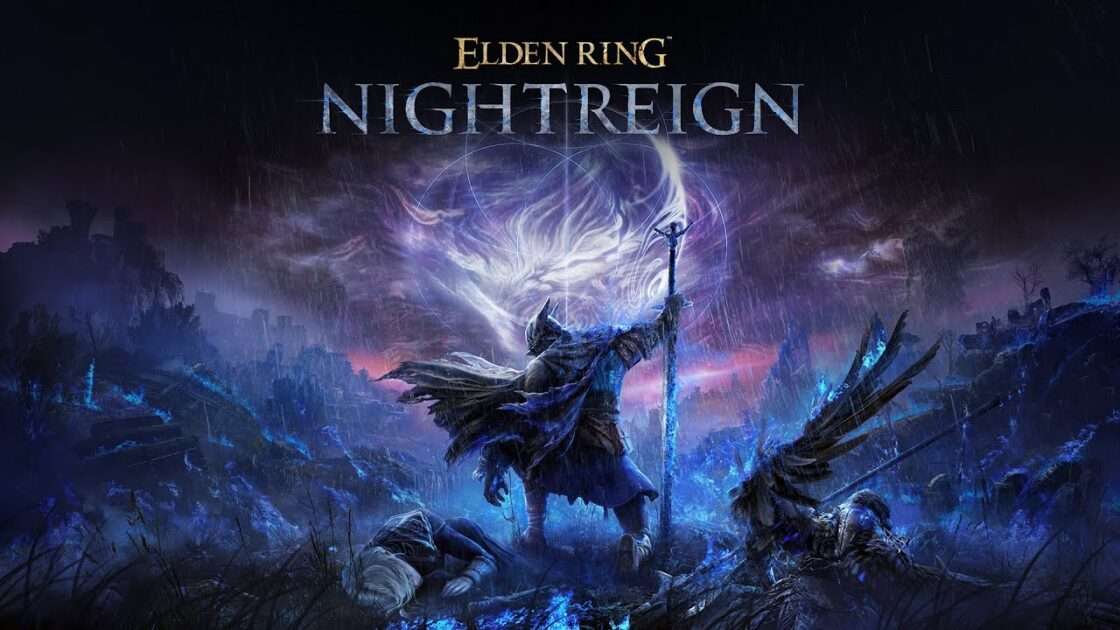









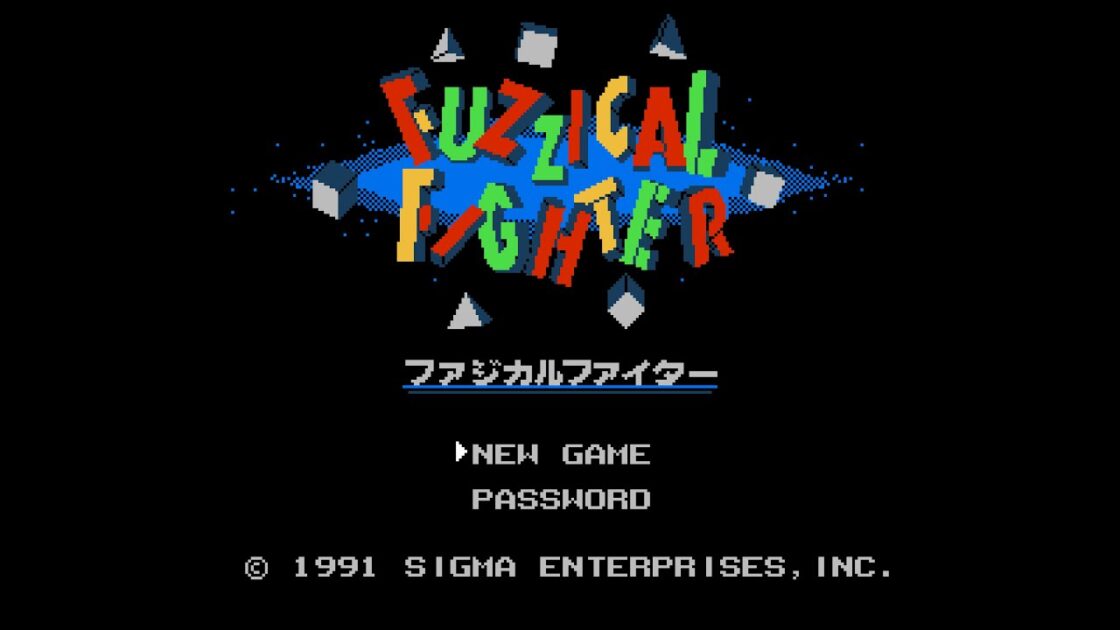



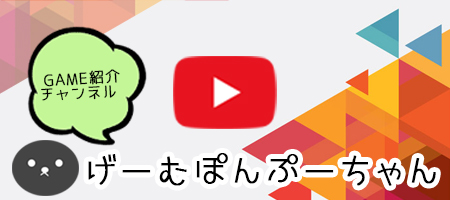
コメントを追加